Deep Research発表から半年──生成AIの進化と経営者に問われるリテラシー
- yuki kato
- 2025年8月17日
- 読了時間: 4分
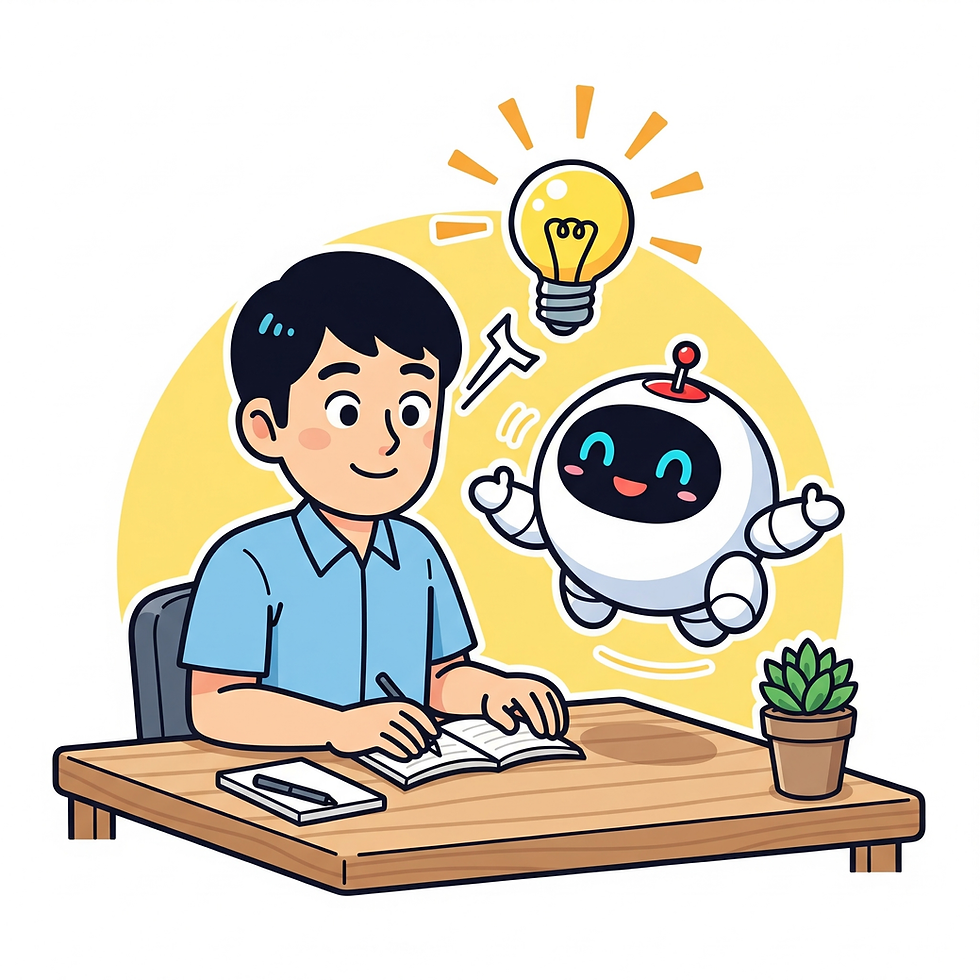
2025年2月2日。OpenAIが発表したDeep Researchは、AI業界に大きな衝撃を与えました。
AIが自律的に調査を行い、引用付きのレポートを生成する──それはこれまで人が何時間もかけていた作業を数分で済ませてしまう画期的な仕組みでした。
例えば、小さな会社で「新しい補助金制度が出ているから調べておいて」と社員にお願いすれば、数日かかることも珍しくありません。しかしDeep Researchなら、制度の比較表をまとめ、申請のポイントまで整理してくれる。中小企業にとっては、人手不足を補う外付けの頭脳のように映ったのです。
あれから半年。AI業界はどう進化したのか。そして我々経営者にとって何が本当に大事なのか。
■ ツール大爆発!半年で2,000から5,000へ
半年前の時点で、生成AIツールはすでに約2,000種類存在していました。ところが今では5,000を超えるモデルやアプリが登場しています。
数字で見ても拡大の速さは歴然です。
Fortune500企業の92%が生成AIを導入
エンジニアの95%が生成AIでコードを書いている
つまりAI活用は特別な大企業の話ではなく、すでに一般的なビジネス基盤へと広がっているのです。
ある経営者仲間は「営業資料を作る時間が3分の1に減った」と話していました。以前は営業社員が一日かけて作っていた提案書も、今はAIに一次案を作らせ、人が仕上げるだけ。浮いた時間を顧客訪問に充てられるようになり、結果的に受注率も改善したと言います。
■ 性能よりも実装力が試される時代へ
Deep Researchが登場した当初は、誤情報や信頼性に不安を抱く声も多くありました。私自身も最初に試したとき、引用の出典が怪しく「これでは使えない」と感じたことがあります。
しかしこの半年で改善が進み、AIは単なる会話相手から外部記憶・調査装置へと役割をシフトしました。調べた情報をただ並べるのではなく、比較・要約・整理まで自動でこなすようになっています。
経営の現場に置き換えるなら、
新商品を出す前の市場調査
補助金制度の比較検討
求人広告やブログ記事の草案作成
顧客へのニュースレターの下書き
こうした人手を割いていた情報作業を、まずAIに一次案を出させ、その上で人が判断するやり方が、すでに成果を出し始めています。
私のクライアントの建設会社では、求人広告をAIに何パターンか作成させ、社員が自社らしい表現を加えて完成させています。その結果、応募率が向上し「AIが作る広告は冷たい」という懸念も消えたそうです。
■ 成果を分けるのはリテラシー格差
それでもAIは思ったほど役に立たないと感じる人がいるのも事実です。
その原因はAIの性能不足ではなく、使う側の姿勢にあります。
リテラシーが低い人は、AIを答えを出してくれる存在として依存し、誤情報に振り回されます。
リテラシーが高い人は、AIを拡張装置と位置づけ、材料を効率よく集め、自らの判断力を高めています。
同じツールを使っても結果が違うのは、ここに理由があります。
先日ある経営者が「AIで広告を作らせたけど成果が出ない」と嘆いていました。よくよく聞いてみると、出てきた文章をそのままコピペして出稿していたのです。これでは他社と差別化できず、むしろ凡庸な広告になるのは当然です。AIはあくまで土台を作る役割であり、人間の目と経験で磨き上げる工程を省いてはいけないのです。
■ 小規模事業者への具体的ヒント
ここまでの話を現場に落とし込むなら、次のような実践が有効です。
1. 毎日の情報収集をAIにアウトソースする
補助金制度や業界ニュースをAIに要約させ、自分は判断だけに集中する。
2. 営業や採用の一次資料をAIに作らせる
下書きはAIに任せ、人は自社らしさを加えるだけで時間短縮。
3. AIの出力を必ず検証する習慣をつける
そのまま使わず、自分の目で必ずチェックする。これがリテラシーの第一歩。
こうした小さな積み重ねが、半年後には大きな差となって表れます。
■おわりに…
半年前の革命で広がったのはAIの数と機能の可能性でした。ツールの種類は2,000から5,000へと増え、大企業だけでなく小さな会社の現場でも活用が進んでいます。
しかし、次の半年を決めるのはAI自身の進化ではありません。大事なのは、経営者である私たちがどう使うかを学び、実践していくことです。
AIは人の代わりではなく、意思決定を支える拡張装置。
そのリテラシーを磨くことが、これからの時代を生き抜く最大の武器になるはずです。








コメント