損切出来ない心理
- yuki kato
- 10月30日
- 読了時間: 3分

埋没費用(サンクコスト)とは、すでに支払ってしまい回収できない費用のこと。
経済学ではよく知られた概念だが、実際には企業経営やマーケティング、プロジェクト運営などあらゆる場面で人の判断を狂わせる。
理屈では「無視すべきコスト」と分かっていても、感情がそれを許さない。
例えば、うまくいっていない広告施策をここまで投資したんだからと続けたり、成果が出ない新規事業をもう少しやればと延命したりする。
過去に使ったコストを取り戻そうとする心理が、未来の合理的判断を奪う。
■埋没費用の費用とはお金だけではない
埋没費用の費用には、お金だけでなく時間や手間、労力、感情、信頼、プライドなども含まれる。
むしろ、ビジネスの現場で最も厄介なのはこの見えない費用だ。
たとえば、数年かけて育てたチームやブランドを方向転換することには、金額以上の心理的負担がある。時間と労力を注いだ分だけ、やめる痛みも大きくなる。経営者が今さら変えられないと思う瞬間、その判断にはすでにサンクコストの影が差している。
この感情の罠は、恋愛にも似ている。ここまで一緒に過ごしてきたから別れられない、という心理構造と同じだ。埋没費用効果は、人間が損を避けたいという本能に根ざしている。だからこそ、数字よりも心の整理が難しい。
■ビジネスモデルに組み込まれたサンクコスト構造
実はこの心理を逆手に取ったビジネスモデルも多い。代表的なのがサブスクリプション(定額課金)やポイント制度、ゲームの課金システムだ。過去に積み上げたデータや特典がやめる理由を失わせ、継続を促す構造になっている。
教育・資格ビジネスも同様で、受講料を支払った受講者は元を取らないとという意識で途中離脱しづらくなる。
企業から見れば継続率が上がる仕組みだが、消費者側から見れば冷静な判断を妨げる要因にもなる。
つまり、やめられない仕組みを設計した側が利益を得る。多くのサブスク企業が「やめづらさ」をどこまで心理的に設計しているかを知ると、その巧妙さに驚く。
■経営判断を歪める「正しさへの執着」
埋没費用効果の根底には、自分の判断を間違いだと認めたくないという心理がある。
経営者はこのバイアスが強く働く。過去の判断を否定することが、まるで自分自身を否定するように感じてしまうからだ。
この状態を避けるには、感情ではなくルールで判断することが重要。KPIが一定水準を下回ったら撤退、投資回収率が目標値を下回ったら方針転換など、事前に基準を決めておく。株式投資でいうストップロス(損切り)と同じ考え方だ。
判断基準を明確にし、撤退を「失敗」と捉えず「再投資へのリセット」と考える。これができる経営者ほど意思決定が早く、結果的にリターンを最大化できる。
■埋没費用を「学び」に変える思考法
優れた経営者は、サンクコストを損失ではなく学習コストと捉える。費やした時間やお金を、次の判断精度を上げるためのデータとして扱うのだ。過去にかけたリソースを、過去の正当化ではなく未来への布石として利用する。
やめる勇気は、未来を選ぶ勇気でもある。撤退は敗北ではなく戦略の一部。
埋没費用効果を乗り越える人こそ、次のステージで本当のリターンを得られる。
とはいえ…徹底的に損切してると、人間関係も切りまくる事になったり…ね。
リテラシーを持って判断できるようになる!
始めなければ、費用は埋没しません。
〜〜〜〜〜〜〜〜
AI未来鑑定士 / リクルートストーリーテラー
合同会社Lepnet 代表社員 加藤勇気
応募を来させるプロの会社。
1日1000円のX投稿代行(投稿+エンゲージ活動まで対応)。
詳しくはウェブへ → https://www.lepnet.biz





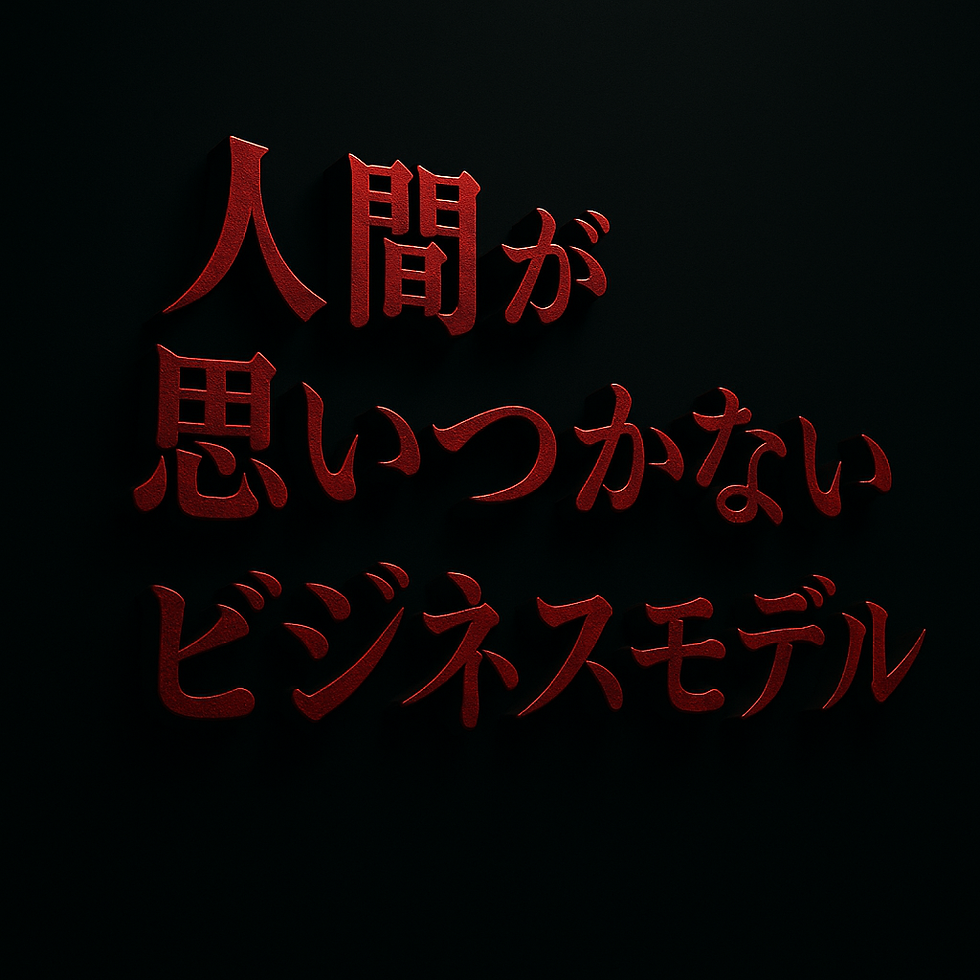


コメント